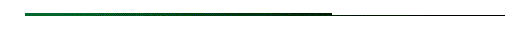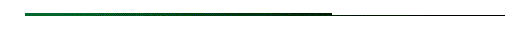北区大阪天満宮夏期例大祭 その4

 境内の一角に藤棚と座敷きがありました。
境内の一角に藤棚と座敷きがありました。
藤棚???季節が違いますね。
実は紫に見えているのは淀川名産のしじみの貝殻です。
この「蜆の藤棚」は江戸時代からの伝統だとか
 座敷きに飾られた人形の一体です。
座敷きに飾られた人形の一体です。
八幡太郎義家です。
源頼朝、義経のお祖父さんで、河内出身の名勇です。
 鎮西八郎為朝です。
鎮西八郎為朝です。
 鬼若丸です。
鬼若丸です。
これは武蔵坊弁慶のことだとか。
これら3体の人形は江戸時代の天神祭の華と呼ばれた
「御迎人形」です。
船渡御の神輿を迎える船の舳先に飾られた人形で
文楽や歌舞伎の登場人物などが題材です。
天神橋商店街と国道1号の交差点に
これらのレプリカが年中飾られています。
江戸時代には50体あったそうですが、
現在は16体だけが残されているそうです。
そのうち14体は大阪府の文化財に指定されており、
天神祭の時に3体ずつ順番に、ここに飾られるとか。
 「猩々舞」の像です。実はこれは昆布などの干物でできています。
「猩々舞」の像です。実はこれは昆布などの干物でできています。
江戸時代の記録をもとに数年前に再現されたそうです。

 座敷きの上に飾られた額の絵とそのアップです。
座敷きの上に飾られた額の絵とそのアップです。
江戸時代に奉納された絵馬に描かれた「尼崎の地車」
の絵をデジタル処理して再現したものだそうです。
その5へ
だんじりレポートへもどる
ホームへもどる